噛み締めが強いと呼吸が浅くなる?筋膜との関係と自律神経への影響とは
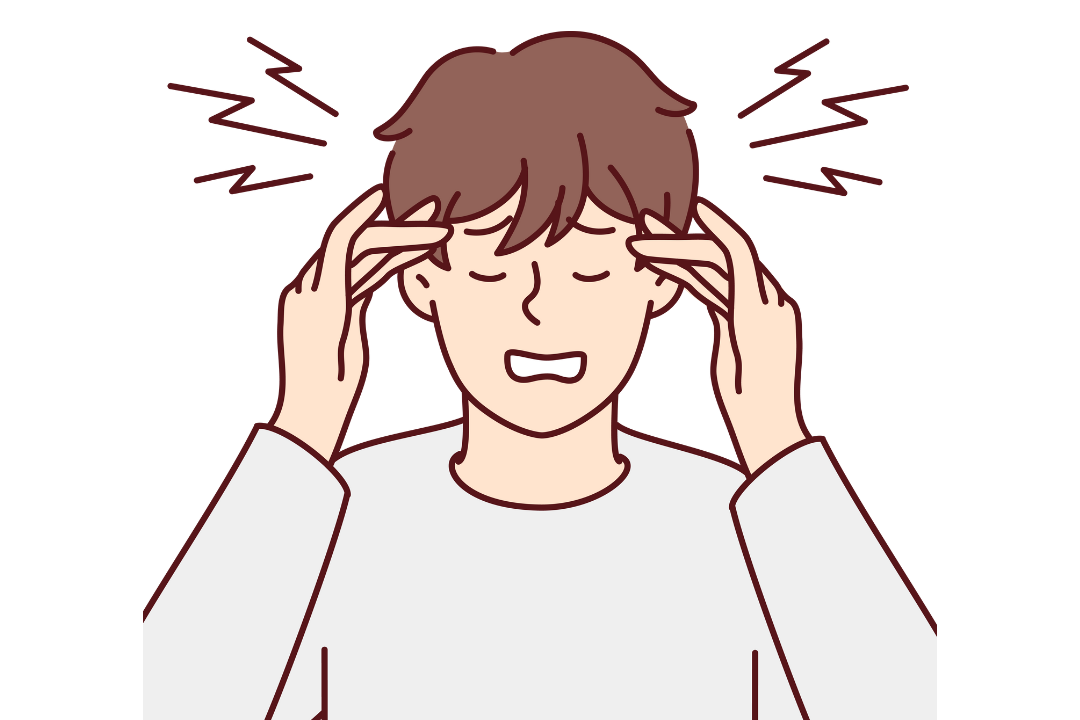
噛み締めが強いと、なぜ呼吸が浅くなるのか?
寝ているときや集中しているとき、無意識に歯をグッと噛み締めていることはありませんか?
この「噛み締め」のクセ、実は呼吸の深さや質に大きく関係しています。
「え、口と呼吸ってそんなに関係あるの?」と思われるかもしれませんが、じつは噛み締めによって首や胸まわりの筋肉が緊張し、呼吸に使う筋肉の動きが制限されてしまうのです。
とくに最近、「なんだか息が浅い」「息苦しさを感じる」という方の中には、噛み締めのクセが原因になっているケースも少なくありません。
かみしめの詳しい記事はこちらから
筋膜のつながりが呼吸に影響する
ここでカギとなるのが「筋膜(きんまく)」です。
筋膜とは、筋肉や内臓を包んでいる薄い膜のことで、全身にくまなく張り巡らされています。この筋膜は、まるで全身をつなぐボディスーツのようなもの。どこか一か所に強い緊張やゆがみが生じると、他の部位にも影響が波及します。
噛み締めによってこめかみや顎、首の筋肉が硬くなると、それに連動して胸や肩まわりの筋膜も引っ張られ、結果的に胸郭(きょうかく:肺が収まるスペース)の動きが制限されてしまいます。
この状態が続くと、呼吸に使う横隔膜(おうかくまく)の動きも小さくなり、自然と浅い呼吸が癖になってしまうのです。
呼吸の浅さが引き起こす自律神経の乱れ
では、呼吸が浅くなると何が起きるのでしょうか?
私たちの呼吸は、自律神経と深くつながっています。深くゆったりとした呼吸は、副交感神経を優位にしてリラックス状態へと導いてくれます。一方、浅く速い呼吸が続くと、交感神経が優位になり、緊張やイライラ、不安感などを感じやすくなります。
つまり、噛み締めが強くなる → 筋膜を介して胸や横隔膜の動きが制限される → 呼吸が浅くなる → 自律神経が乱れる、という流れができてしまうのです。
この悪循環が長く続くと、「なんとなく体がだるい」「眠っても疲れが取れない」といった慢性的な不調にもつながりかねません。
「噛み締め」に気づくことが改善の第一歩
噛み締めは多くの場合、無意識に起こっています。だからこそ、まずは「今、力が入っていないか?」と自分自身に気づくことが大切です。
起きているときに気づいたら、舌を上顎につけ、奥歯の接触を軽く離すだけでも緊張がやわらぎます。
また、口を「ポカン」と軽く開けた状態を意識するのも効果的です。
夜間の噛み締めがひどい場合は、歯科医に相談し、マウスピースの装着を検討してもよいでしょう。
呼吸を取り戻すと、心と体が変わる
呼吸は、私たちの体と心をつなぐ「橋」のような存在です。
深く息を吸って、しっかり吐けるようになると、それだけで頭がスッキリしたり、肩の力が抜けたりするのを感じたことがある方も多いはず。
噛み締めをゆるめ、筋膜の緊張をほぐすことで、呼吸の質は大きく変わります。そして呼吸が変わると、日常のパフォーマンスやメンタル面にも良い影響が出てきます。
ちょっとしたクセの積み重ねが、体調や心の状態にまで波及している――そんな視点をもって、自分の体にやさしく目を向けてみてください。
まとめ
噛み締めは口元の問題だけではなく、呼吸や自律神経にまで影響を与える“全身の問題”でもあります。
筋膜のつながりを意識しながらケアしていくことで、呼吸の深さ、そして心身のバランスも整っていくでしょう。
毎日のちょっとした気づきとケアで、自分の呼吸を取り戻していきましょう。
